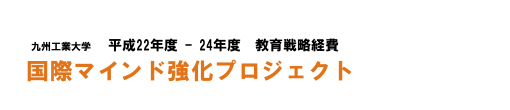トップページ > 研究マインド強化プログラム > 下水汚泥溶解細菌の分離・同定
下水汚泥溶解細菌の分離・同定
概 要
微生物の基本的な取り扱い技術からはじまり、下水汚泥溶解菌の分離・同定および性状、さらにはその汚泥溶解率の測定について、実際の細菌株を用いて種々の技術を習得する。
コース内容
1、学 習
- ・微生物の取り扱い方
- ・微生物のスクリーニング、
培養や保存法など - ・形態観察
- ・生化学/生理学的試験
- ・16S rRNA遺伝子のDNA相同性解析
- ・汚泥溶解率の測定
- ・下水汚泥中の有機物の測定
2、実 習
- ・試薬や培地などの取り扱い
- ・液体および寒天培地と試薬を使用し、無菌操作技術と微生物の培養技術を習得する
- ・顕微鏡を使用して微生物の形態を観察する
- ・様々な基質を用いて、微生物の生化学/生理学的性状を解析する
- ・DNAシーケンスによりDNAの塩基配列を解読し、得られた配列を基にコンピュータによるDNA相同性解析を行う
- ・汚泥溶解細菌を使用して、下水汚泥の溶解率を測定する
- ・Lowry法によるタンパク質分析、フェノール-硫酸法による糖類分析、ガスクロマトグラフィーを利用した脂質分析をそれぞれ行う
実施形態およびスケジュール
学習については、パッケージで指定する書籍および参考文献を用いて行う。学習の結果はセミナー形式で発表し、その後レポート形式でまとめて提出する。実験については、パッケージで指定する段取りに従って実施する。週に1度の定期報告の他に、必要に応じて随時打ち合わせを行う。
コースオプション
実習課題に関しては、実際のテーマに対して、個別に相談の上決定する。
履修上のポイント
はじめに、微生物の基本的な取り扱い技術を習得する。つぎに、細菌学の分野で技術・研究の際に実際に使用される生化学/生理学的試験、DNA相同性解析や生体高分子の分析などについて理解を深める。
必要となる基礎能力
本演習には、微生物学および分子生物学に関する、基礎知識を得ていることが望ましい。
研究テーマとの組合せ事例
下記のような研究テーマとの組み合わせが例として挙げられる。
「有用細菌株の分離・同定およびその性状」
「下水汚泥溶解に関する最適化」
「有機酸の分析法」
「有用細菌株の分離・同定およびその性状」
「下水汚泥溶解に関する最適化」
「有機酸の分析法」
成績評価基準
下記の項目について5段階評価で得点をつける。平均が3.5を上回れば合格とする。
- (1) 微生物の取り扱いに関する理解度
- (2) 生化学/生理学的試験および、DNA相同性解析に関する理解度
- (3) 生体高分子の分析に関する理解度
- (4) 最終プレゼンテーションおよびレポート