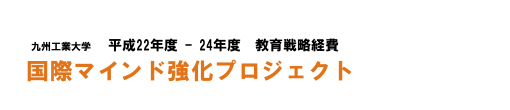トップページ > 研究マインド強化プログラム > 固体力学分野の有限要素解析入門
固体力学分野の有限要素解析入門
概 要
固体力学分野の境界値問題を解きたいとき、定評のある有限要素法のソフトウエアを使いさえすれば安心だという考えは大きな誤りである。このコースでは、入門者がどんな手順を踏んでいけば正解に無事たどり着けるようになるのか、講義と実習を通して教育する。
コース内容
1、学 習
ベクトルとテンソルの計算
固体力学の微小ひずみ弾性問題における基礎的関係式と仮想仕事の原理
有限要素法による数値解法
固体力学の微小ひずみ弾性問題における基礎的関係式と仮想仕事の原理
有限要素法による数値解法
- ・形状関数
- ・変位―ひずみマトリックス
- ・要素剛性方程式
- ・全体剛性マトリックス
- ・全体剛性方程式の解法
2、実 習
ソフトウエアの起動、利用、停止の方法
解析実習
解析実習
- ・解析の基礎
- ・幾何学的形状の作成
- ・材料特性の付与
- ・要素選択
- ・メッシュ生成
- ・境界条件設定
- ・解析実行と結果表示
- ・解の信頼性の確認
実施形態およびスケジュール
夏季休業期間を利用して、連続する5日間(4時限分×5回)に講義と実習を行う。講義には有限要素法の教科書を用いる。実習は1つの例題と2つの課題からなる。2つの課題では各自がソフトウエアを用いて解を求めるとともに、その解が正しいかどうか別の解法を利用して比較する。その結果を指導教員に報告して、妥当な計算結果かどうか確認する。
コースオプション
実習課題に関しては、用意した2つの課題のほか、各自が用意した課題を解いてもよい。
履修上のポイント
正しい解を導けたと確信が持てるようになる方法を習得するのがこのコースの目的である。材料力学の教科書や便覧を調べたり、経験豊富な専門家の助言を受けたりして、有限要素法で正しい解が得られるようにする。
必要となる基礎能力
材料力学の素養があることが望ましい。ない場合には事前に最低限の知識は習得しておくこと。また、「生体力学」や「計算バイオメカニクス演習」を受講しておくことも有益である。
研究テーマとの組合せ事例
下記のような研究テーマとの組み合わせが例として挙げられる。
「生体代替材料の開発」
「MEMS構造物の開発」
「福祉機器の開発」
「電子部品の高集積化」
「生体代替材料の開発」
「MEMS構造物の開発」
「福祉機器の開発」
「電子部品の高集積化」
成績評価基準
下記の項目について5段階評価で得点をつける。平均が3.5を上回れば合格とする。
- (1) 有限要素法の理論に関する理解度
- (2) 実習課題1の達成度
- (3) 実習課題2の達成度
- (4) 解の信頼性の確認方法の習得度